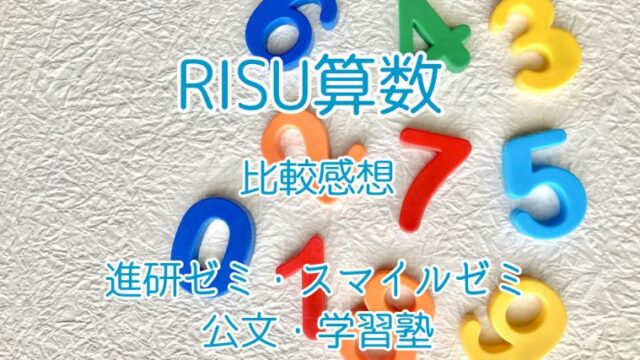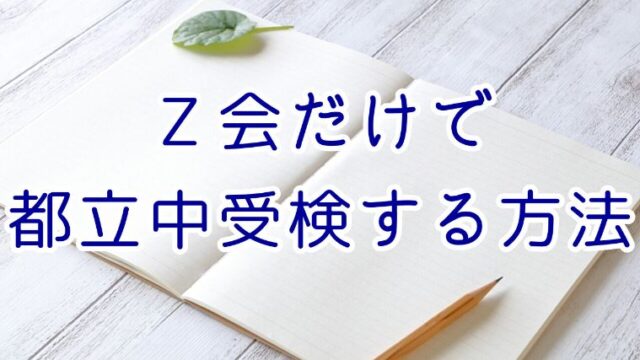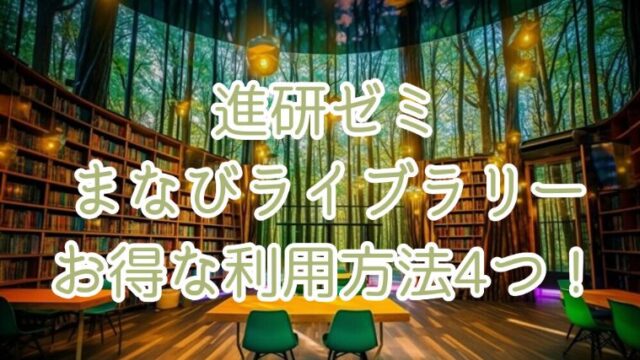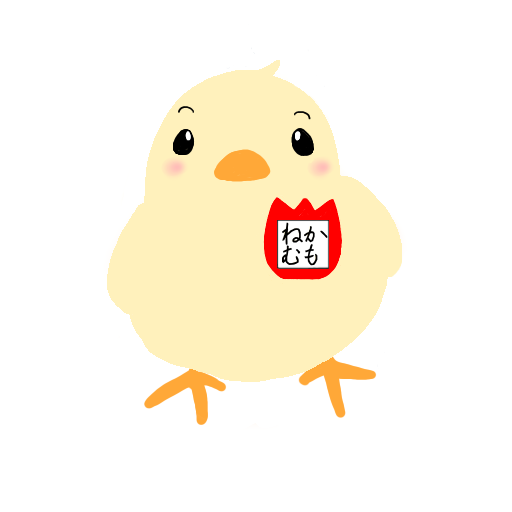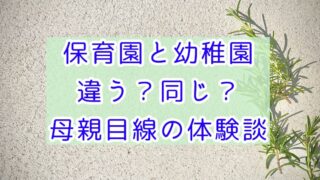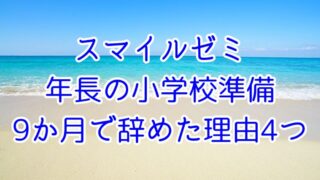公文は学習習慣が身に付き、自然と漢字や計算に自信を持つことができるようになります。
幼児・小学生にとって良い学習システムです。
しかし!
毎日の公文の宿題を、自主的に進んでやってくれる子は果たしてどのくらいいるのでしょうか?
特に、自分の学年以上の進度になったタイミングが一番大変です。
- 日々の親の接し方
- やる気にさせるための具体的な方法
- 公文を続けた先に見えるもの(我が家の場合)


中学受験(受検)を検討中の方に是非読んでほしい、小学校低学年の子におすすめする通信教材6選の記事はこちら。
公文の宿題をやりたがらないのは当たり前
公文は、初めは学年より1つか2つ前の簡単な問題から始まります。簡単なので、1科目5分~10分くらいですぐに解けてしまいます。
その間は、逆に費用がかかっているのに、こんなに早く終えてしまってもったいないと思うくらいなのですが。
自分の学年を超えた問題を解く頃になると、難しくなるので毎日の公文の宿題を進んでやらなくなってきます。
声かけをして、すぐに取り掛かってくれれば何も大変なことは無いのですが、そうはいかないのが子どもですよね。
親が公文の宿題をやらない子にイライラする理由をまとめてみました。
- ダラダラするだけの時間がもったいないと感じる
- いざ宿題に向き合っても、途中で本を読んだり遊び始めてしまう
- 宿題が終わらないせいで、夕飯を食べる時間や寝る時間(タイムリミット)が遅れてしまう
- 子どもが公文の宿題をやらなくても平気な顔をしている
- 小4までに3学年先まで学習を進めたい、などの希望が計画通りに進まない
1科目5枚だけなのに、集中できない我が子にあきれてしまうことが多々ありました。
週2回の公文教室では集中して終わらせて帰ってくるので、問題が難しすぎて解けないというのではないです。
頭を使った単純作業が面倒でやる気がおきないというのが、宿題ができない理由です。
公文の宿題への親の毎日の向き合い方

公文の先生に報告・相談する
できなかった宿題は、先生にお返ししますよね。
その時に、付せんなどの簡単なメモを添えて、子どもの家での学習態度や状況を報告しましょう。
公文では年に2回の個人面談がありますが、子どもの学習態度はお知らせしておいたほうが、先生も子どもに声かけがしやすくなります。
子どもの家での学習の様子を伝えて、子どもにとって甘えが利かない「先生」という立場から、子どもにしっかり言い含めてもらったり、もしくは宿題の枚数や進度を調節してもらいましょう。
公文を学習するメリットは、第三者である先生が、子どもと向き合って話し合ってくれることです。
通信教材には無いメリットなので、報告・相談という形で先生に子どもの状況をお伝えしましょう。
良い先生は、親に精神論を説きません。宿題の枚数や進度(レベル)を調節してくれます。
小学2年生の息子が3桁の引き算につまずいた時、先生が対応してくれたエピソードを書いていますので、こちらも参考にしてくださいね。
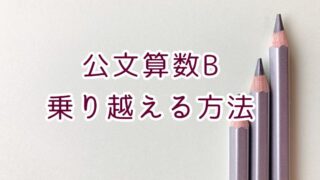
私は後で知ったのですが、宿題の負担を減らすため、算数にてこずっている時期、敢えて先生が公文国語の漢字のページを減らして、物語を読むだけのページを多めに出してくれていました。
さりげなく「宿題を毎日続けられるようにする」ためのフォローをしてくれていたんですね。
子ども・親・先生それぞれにとっていい方向に行けるような、ほどよいコミュニケーションがとれる先生が最重要です。
信頼関係を結ぶには、初めは親も我慢が必要です。1年くらい様子をみたら、先生の合う合わないはわかるんじゃないかなと個人的に感じます。
公文の先生は、教室によってキャラクターがだいぶ異なるので、後の章でも書いていますが、合わない場合は公文教室を変えるのも1つの手です。
感情的に怒鳴らない・怒らない
親にとって一番難しいことで、精神論にもなってしまいますが、感情的に怒らないことが大切です。
イライラしても、ジョークを交えて怒ってください。
公文の宿題ができなくても、子どもは元気に育ちます。
親が怒ると余計に「自主的に勉強する子ども」からは遠ざかってしまいます。
「も~、私は今プンプンだよ!マサラタウンに修行に行ってこい!サトシと旅に行ってこい!」とポケモン好きの息子に言うと、息子は喜ぶし、私は自分に笑えてきて我に返ります。
ちなみに、偉そうに書いている私ですが、寝不足だったり疲れていたり、忙しくて時間が無かったり・・・ストレスをためていると、ヒートアップして爆発することがしばしばあります。
公文の宿題の時間を子どもと話し合って決める
子どもが主体的に決めることがポイントです。
子どもが「朝にやる」と決めたら、そのサポートに徹します。朝起きられなくて、できなかったら、次はどうすればいいか話し合う。
「帰ってきておやつ食べてゲームを終えたら、夕飯までの時間にやる」と決めたら、ゲームを終えたら声をかける。
結局ダラダラして終えられなかったら、じゃあどうすればいいかを話し合って決める。
「ゲームの前に宿題をやる」と本人が決めたら、翌日にゲームをやり始める前に、声かけをして宿題を促す。
帰宅して「ゲームしたい」となったら、昨日決めた公文をやる時間じゃないの?と聞いてみる。
結局ダラダラして宿題を終えられなくて・・・じゃあどうしようか、の無限ループです。
根気のいる作業ですが、その繰り返しです。
できなかった時でも怒らずに、子どもなりに頑張って考えていることを褒めてあげると、少しずつ子どもが変わってきます。
ダラダラは放っておく
子どものダラダラを傍で見続けるのは、なかなかつらいものです。
公文の宿題は、集中すれば1科目20分~30分で終わるのに、なぜやらないのかと親は思ってしまいますよね。
ついつい小言を言いたくなります。実際、私は言うことがよくありました。でも、余計に自分の感情がヒートアップしてしまい、良いことがありません。
親が忙しい時は、もう子どものダラダラを放っておきましょう。
ひたすらダラダラするのも大事です。保育園・幼稚園・小学校という親と離れたコミュニティーで、子どもは子どもの世界でとっても頑張っています。
ダラダラするということは、この子にはダラダラする時間が必要なのだと自分に言い聞かせて、親は親の用事に集中しましょう。
終わるまで横に張り付く
もし、親に時間の余裕がある時は、横に1時間でも張り付いて、公文の宿題をやっているところを見てあげましょう。
特に、幼児の場合は、親が横で見ててあげないと、宿題ができない子のほうが多いのではないでしょうか。
我が家は、1人目は年少秋から公文国語を始めました。当時は働いていたので、18時まで保育園に預けつつ、幼児の公文の宿題を見てあげるのは、なかなかハードワークでした。
そのため、2人目の時には無理と思い、2人目が公文を始めたのは小学生からです。年長の頃だけスマイルゼミ![]() をしていました。
をしていました。
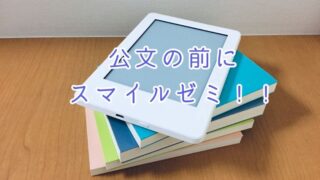
できない日があってもスルーして大丈夫
夕飯が遅くなってしまったり、寝る時間がずれこんでしまうことが、ストレスの原因ではありませんか?
公文の宿題よりも、夕飯の時間や睡眠時間を優先すると割り切ってしまいましょう!
1週間のうち、平日2日間は公文教室でしっかり問題を解いています。
例えば残りの平日3日間、全然宿題ができなかったとしても、学校がお休みの土日さえちゃんとやっていれば、1週間のうち4日間はしっかり勉強しているのです。
気持ちが乗らなくて、いまいち頑張れない時期は誰にでもあります。
できない日があっても、親がスルーしても全然大丈夫なのです。
公文の宿題をやる気にさせるための具体的な方法

漢字検定・算数検定を受ける
その学年相当の進度を終えそうなタイミングで、漢字検定や算数検定に申し込みましょう。
漢字検定や算数検定の過去問を購入して、試験の2か月前くらいから、少しずつ親子で取り組みます。
「合格証書」をもらえると、子どもは頑張ってきた自分に自信が持てるようになります。
毎日コツコツ継続することの大切さを体感して、これからも頑張ろうって気持ちが芽生えるきっかけになるはずです。
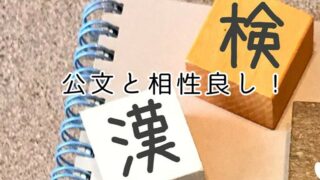
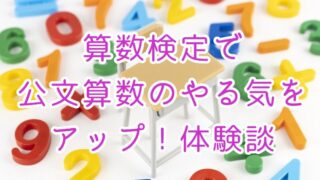
児童館など場所を変えてみる
家の中ではなく、別の場所で宿題をやることを提案してみるのも1つの手です。
児童館など、宿題をやっても良いスペースがある場合は、そこで公文の宿題をやってきてもらいましょう。
ついつい、宿題はやらずに遊んでしまうこともあるでしょう。
ですが、意外と家以外の場所だと集中できるようで、我が家はこの方法が解決の1つの手段になっています。
他の子に、公文の宿題をやっているところを見られることが、ちょっとした優越感やプライドを刺激されるみたいです。
公文教室を変えてみる
公文の先生は、公文教室によってだいぶキャラクターが異なります。
私は2つの公文教室に子どもたちを通わせたことがあり、他に1つ見学にも行っていますが、先生は3者3様でした。
- ベテランのちょっと子どもたちから恐れられている先生
- きめ細やかに子どもに合わせてくれる優しい先生
- 子どもに合わせてあえて厳しく接したり、優しく接したり、臨機応変がうまい先生
もし、通える範囲にもう1つ教室があって、子どもが違う教室なら今より頑張れそうと言うのならば、公文教室を変えてみるのも1つの手です。
公文は転出から3か月以内なら、公文教室の変更に新たな出費はかからないので、気軽に変更ができます。
通信教材を併用する・通信教材に乗り換える
公文は同じようなプリントをひたすら反復して解くスタイルです。
どうしても向き不向きがあります。
- 公文と併用してタブレットの通信教材を試してみたり
- 公文を休会して思考型のワークに切り替えてみたり
※公文の休会期間は、最長3か月です
公文にこだわらず、その子に合いそうな自宅学習方法を新たに検討することも大切です。
色々試してみたら、結局公文に戻ってきたってこともありえます(実体験済み。)
Z会
反復作業が苦手なタイプの子は、もしかしたらZ会が合っているかも。
Z会は質のいい(=思考力を試される)良問ばかり。
中学受験に対応できる唯一の通信教材でもあり、公文よりZ会のほうが後々の受験には効果てきめんです。
Z会の通信教育 小学生コースを実際にやってみた感想は、
「自主的にZ会の問題を解ける子は、親が放っておいても勝手に勉強するタイプだ」ということ。
うちの子は、公文を3か月休会して、Z会を試した時期がありました。そして結局公文に戻りました(笑)
「自分は公文を続けたいんだ」という自覚を持ってくれたのが、我が家がZ会を試して良かったことです。
紙コースよりは、タブレットコースのほうが子どもの食いつきもいいし、親もラクです。
質のいい良問を無料でもらえます。ぜひ試してみてくださいね!

スマイルゼミ
スマイルゼミ![]() は、学校の成績アップが目的の場合、一番に検討をおすすめする教材です。
は、学校の成績アップが目的の場合、一番に検討をおすすめする教材です。
かさばってしまう余計な付録が無いし、タブレット1台で全て完結するので、親の負担がほとんどありません。
難易度的にも、「進研ゼミよりは難しく」「Z会よりは簡単」というちょうど良さ。
専用タブレットの書き心地No.1。紙に書く感覚でタブレット学習ができます。
専用タブレット代は、1年使えばがかなり割安になります。
辞めた後は普通のアンドロイドタブレットとして利用可能。
タブレット学習の最大のメリット、視覚的に楽しく勉強ができて、学習習慣がつけられます。
しかも公文と同じように、学年以上の進度をどんどん勉強できる「コアトレ」もついている。
無学年学習といって、その子の進度に合わせて先に進める教材が、タブレット学習でも実現します。
進研ゼミ
言わずと知れたチャレンジタッチです。
【進研ゼミ小学講座】は、学校の授業と同じくらいの難易度なので、公文で学年より先に進んでいる子の場合、1週間もしないで月の範囲を終えてしまいます。
ただ、公文にはない「理科」「社会」などの授業内容も予習できるし、さまざまなコンテンツが充実しているのでワクワクできます。
うちの子は、チャレンジタッチの勧誘マンガに憧れていたこともあり、公文を頑張るご褒美として進研ゼミを併用した時期がありました。
これは公文継続のモチベーション維持に効果がありました!
進研ゼミを受講して、一番良かったのは電子書籍読み放題の「まなびライブラリー」です。
当時、学童が合わずに放課後を1人で家で過ごすことが多かった娘にとって、児童文庫に親しむきっかけになりました。
公立中高一貫校受検に有利な多読・速読の能力が、本好きになると自然と習得できます。
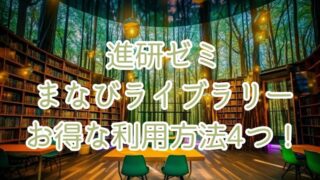
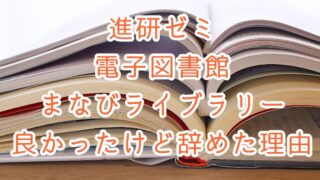
ワンダーボックス
ワンダーボックスは、他の通信教材とは毛色が違います。
公文には無い「思考力・ひらめき力」を、遊びの延長のような感覚、つまりゲーム感覚で身につけていきます。
学校の勉強とは全く連動しておらず、一見するとただのゲーム。
でも、後々の中学受験で必要になる立体図形の空間認識の感覚や、論理を組み立ててゲームを攻略することでプログラミング的思考を自然と育ててくれることを実感しました。
なので、我が家は細切れにではありますが、ワンダーボックスを利用しています。
手持ちのタブレットやスマホで、最短2か月から利用可能なので、公文を続けるためのご褒美的な位置付けで併用すると子どもが喜びます。
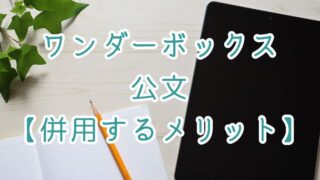

「いつまでにやらなきゃいけない」「ここまでやらなきゃいけない」このような縛りは一切無し。
「ねばならない」は、公文で十分なので、ワンダーボックスはひたすらゲームアプリの1つのような扱いで、子どもたちは遊びながら学ぶことが出来ます。
中学受験(受検)を検討中の方に是非読んでほしい、小学校低学年の子におすすめする通信教材6選の記事はこちら。
まとめ
公文の宿題は、親子ともに苦労しますが、得られるものも大きいです。
進度に関わらず、公文を試行錯誤してなんとか継続してきた体験こそが、子どもにとって大きな自信になります。
- 勉強を継続した先に、達成感や頑張った分の何倍もの嬉しさがあると本人が実感
- 漢字や読解、計算に自然と強くなること
受験に挑む前の下地作りができます。
3学年先など、目指していた進度まで到達しなかったとしても、日々の宿題とどう向き合うか試行錯誤した本人の経験が、後々の大学受験で絶対に役に立ちます。
「公文は先に先に進度を進めないと、中学受験に意味がない」とか「公文を反射的に早く解けるだけでは、中学以降は役に立たない」とか、色々言われちゃう公文ではあります。
ですが、はっきり目には見えないけれど、子どもを成長させてくれるものがあるから、私は公文って良いなと感じています。
公文で親がイライラしたってOKなのです。子どもとたくさんバトルして、話し合って、継続することの達成感を味わいましょう!
中学生以降、親が勉強に関われなくなる前に、親子で色々試行錯誤して公文の宿題と向き合っていきましょう!
とは言っても、公文辞めようかな・・・と思う方、こちらの記事も参考にしてくださいね。
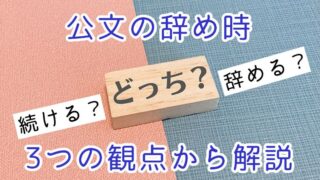
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
中学受験(受検)を検討中の方に是非読んでほしい、小学校低学年の子におすすめする通信教材6選の記事はこちら。

https://kamonemudo.com/kumon-d150-after4/